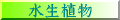file: 001 Title: トゲウオ類の巣
file: 001 Title: トゲウオ類の巣 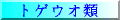
 |  |  |  | 「トミヨ属淡水型の巣と産卵」 JPN: トミヨ属淡水型種鱗板不連続型 (旧称:イバラトミヨ) End (IUCN):SCI: Pungitius sp. Freshwater type ENG: RUS: End (JPN): End (Hokkaido): 左写真: 巣に入ろうとするメスをせかしているオス。 特徴 ・ 背棘は9-10本。 ・水中で観察する際の重要な識別ポイントは、 オスの腹棘内側が青-水色を呈している点。 注意 ・ |
 |  |  |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  | 「イトヨ属太平洋型の営巣」 JPN: イトヨ属太平洋型種河川型 (旧称:イトヨ) End (IUCN):SCI: PGasterosteus sp. Pacific ocean form ENG: RUS: End (JPN): End (Hokkaido): 左写真: 巣の中に水を送り込んでいるオス。 特徴 ・ 背棘は3本。 ・水中で観察する際の重要な識別ポイントは、 うーーん 注意 ・ |
 |  |  | 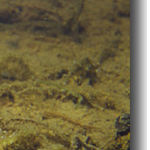 | |
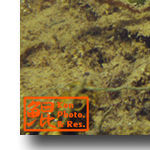 | 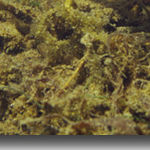 |  | 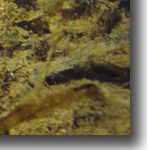 |
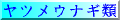 -
-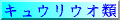 -
-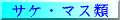 -
-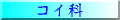 -
-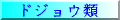
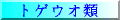 -
-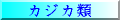 -
-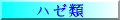 -
-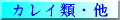
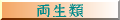 -
-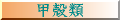 -
-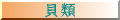 -
- -
-